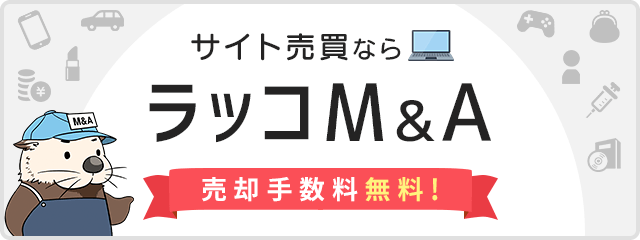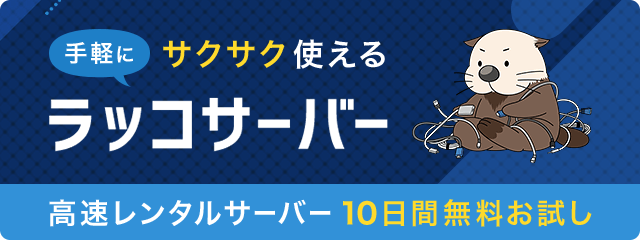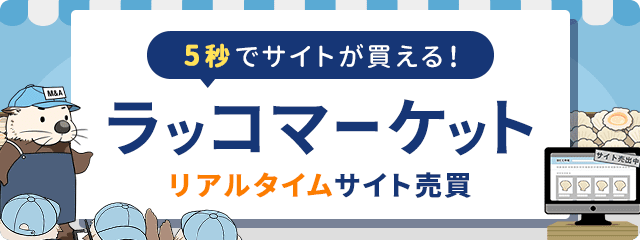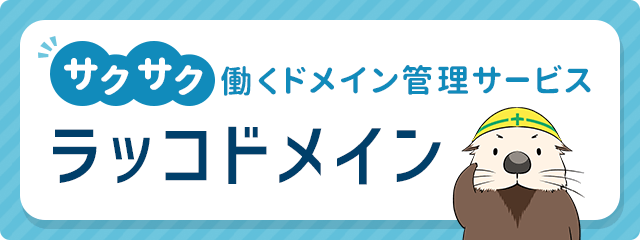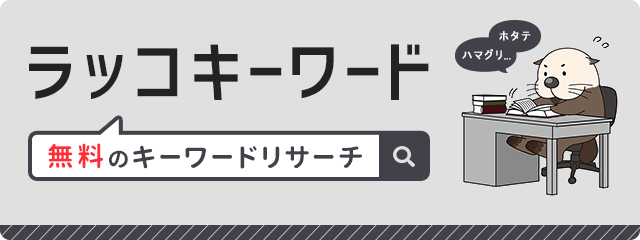Web担当者やブロガーの皆さん、SEOのキーワード選定でこんな壁にぶつかっていませんか?
- 「『鉛筆 削り方』と『鉛筆 とがらせ方』、両方で上位表示したいけど、記事は分けるべき?」
- 「関連するキーワードを1ページにまとめたいけど、SEO評価が分散しないか不安…」
- 「そもそも『1ページ1キーワード』の原則って、どこまで守るべき?」
結論からお伝えします。
複数のキーワードで「ユーザーが知りたいこと(検索意図)」が同じなら、1つのページでまとめて対策すべきです。
やみくもにキーワードごとにページを量産したり、逆に検索意図の異なるSEOキーワードを1ページでSEO対策したりしようとするのは逆効果です。
この記事では、「複数キーワードをまとめるべきか?」を判断するための基準と、SEO効果を最大化する実践テクニックをプロの目線で徹底解説します。
この記事を書いた人:ラッコ株式会社 SEOメディア運用担当者
自社メディアでSEO上位表示記事を作成し、複数キーワードで上位表示を達成した実績多数。
2025年でも通用するSEOメディア運営ノウハウをもとに執筆します。
目次
SEOの「1ページ1キーワード」原則とは?

SEOで言われる「1ページ1キーワード」とは、文字通り「キーワードを1個だけ使え」という意味ではありません。
正しくは「1ページ = 1つの主要なテーマ(トピック)」という意味です。
なぜなら、Googleもユーザーも「この記事が何について書かれているか」が明確なページを好むからです。
- ユーザーにとって: 記事を開いた瞬間に「自分の知りたいこと(テーマ)が書いてある」と分かりやすい。
- Googleにとって: 「この記事は【〇〇】というテーマの専門的なページだ」と認識しやすく、評価が定まりやすい。

「1キーワード=1ページ」ではなく「1テーマ=1ページ」という考え方が正解です!
どこまでを1テーマとして良いのか

「どこまでのキーワードを同じテーマとみなしてよいの?」
と疑問に思われるかと思います。
結論、検索意図が同じか?を基準に判断すればOKです。
そのキーワードを調べたユーザーが解決したい悩み・課題は同じか?という視点で考えます。
- 例1:「鉛筆 削り方」と「鉛筆 とがらせ方」
- これは「1テーマ」と判断できます。
これらは言葉が違いますが、ユーザーが知りたい「行動」や「解決したい悩み」はほぼ同じです。
- これは「1テーマ」と判断できます。
- 例2:「鉛筆 削り方」と「鉛筆 種類」
- これは「別テーマ」です。
前者は「How(方法)」を知りたいのに対し、後者は「What(種類・情報)」を知りたいという、異なるニーズ(検索意図)があります。
- これは「別テーマ」です。
もし「別テーマ」のキーワードを無理やり1ページに詰め込むと、情報が散漫になり、どちらのユーザーも満足させられず、結果的にどちらのキーワードでも上位表示が難しくなります。

ユーザーが求める答えが共通しているか?を軸に判断するのがポイントです。
1ページ複数キーワードの対策可否を判断する基準

SEO対策したい複数のキーワードが「1テーマ」なのか「別テーマ」なのかを、感覚ではなく客観的に見極めるための判断基準をご紹介します。
基準1:「ユーザーが知りたいこと(検索意図)」は同じか?
最も重要な基準です。そのキーワードを検索するユーザーが「最終的に何を知りたいのか」「どんな悩みを解決したいのか」を想像しましょう。
- OK例(検索意図が同じ):1ページで対策
- 「渋谷 ランチ 安い」と「渋谷 昼食 コスパ」
- → 渋谷で安くて美味しい昼食を知りたい
- 「鉛筆 削り方」と「鉛筆 とがらせ方」
- → 鉛筆を鋭くする方法を知りたい
- 「渋谷 ランチ 安い」と「渋谷 昼食 コスパ」
- NG例(検索意図が異なる):ページを分ける
- 「SEO 対策 方法」と「SEO 対策 費用」
- → 「やり方」を知りたい人と「価格」を知りたい人では、検索意図が異なります
- 「ノートパソコン おすすめ」と「ノートパソコン 修理」
- → 「買いたい」人と「直したい」人では、ニーズが全く違います
- 「SEO 対策 方法」と「SEO 対策 費用」
検索意図が異なる場合は、必ずページを分けて、それぞれのニーズに特化した記事を作成してください。
基準2:競合記事は複数キーワードでGoogleにランクインしているか?
検索意図が同じか迷った場合、その答えは「すでに上位表示されている競合サイト」が教えてくれます。なぜなら、それらはGoogleが「ユーザーの意図に合っている」と評価したページ群だからです。
- 対策したい複数のキーワード(例:「鉛筆 削り方」「鉛筆 とがらせ方」)で、それぞれGoogle検索します。
- 表示された上位10サイトのタイトルやページを見比べます。
- 両方のキーワードで共通のページ(サイト)が多くランクインしているかを確認します。
もし、両方のキーワードで共通のページ(サイト)が多くランクインしている場合、それはGoogleが「これらのキーワードは検索意図が近い(1テーマ)=1ページで扱ってOK」と判断している強力な証拠です。
逆に、全く異なるページばかりが上位表示される場合は、検索意図が異なると判断されている可能性が高いため、ページを分けるべきです。
同時ランクインキーワードでサクッと確認!
「基準2:競合(上位サイト)は複数キーワードを同時に扱っているか?」を手動で確認するのは手間がかかりますが、この作業を効率化・高精度化できるのがラッコキーワードの同時ランクインキーワード機能です。
同時ランクインキーワードは、「あるキーワード(A)で上位表示されているページが、他にどんなキーワード(B, C, D…)で一緒に上位表示されているか」を一覧で抽出してくれる機能です。

同時ランクインキーワードで取得できる「関連性」の値が高い場合、Googleが「キーワードA」と「キーワードB, C, D」を非常に近い検索意図(=1テーマ)として認識している可能性が高いことを示しています。
使い方
- ラッコキーワードの同時ランクインキーワードでキーワード(例:「鉛筆 とがらせ方」)を入力して検索します。
- キーワード一覧の中に、一緒に対策したいもう一方のキーワード(例:「鉛筆 削り方」が含まれているか、関連性が高いか(50以上か)を確認します。
判断基準
- 関連性が高い(50以上)場合:「1ページでまとめて対策すべき」と判断できます。
例:「鉛筆 とがらせ方」で上位のページは「鉛筆 削り方」でも上位表示されている。
→これはGoogleが「これらは同じテーマだ」と判断している証拠。 - 関連性が低い(45以下)場合・キーワードが表示されない場合:「ページを分けて対策すべき」と判断できます。
それらのキーワードは、Googleによって「異なるテーマ(別々の検索意図)」として扱われている可能性が高いことを示します。
無理に1ページにまとめず、ページを分けて対策しましょう。

同時ランクインキーワードを使うと、複数キーワードを1ページで対策するか?ページを分けて対策するか?を簡単に判断することができます。
複数のSEOキーワード対策のメリット・デメリット

検索意図が同じ複数のキーワードを1ページで対策することには、明確なメリットと、注意すべきデメリットがあります。
| メリット | デメリット | |
| 概要 | 複数のキーワードから検索流入を獲得でき、PV数・CV数の増加が狙える | 複数のキーワードの検索意図が一致しているか入念な確認が必要。 |
| 詳細 | ・SEO評価(被リンクなど)を1ページに集中できる・関連する多様な検索ワードから流入が見込める・効率的にページを管理できる | ・検索意図が少しでもズレていると、着地した読者の悩みを解決しづらい・わかりづらい記事になりやすいため、どのキーワードでも中途半端な順位になりがち |

検索意図が異なるキーワードを無理に統合して、どちらのキーワードでも上位表示できないのが最大のリスクです。
迷った場合は、「基準2:競合分析」を徹底して行いましょう。
複数キーワードを自然に盛り込むテクニック

複数キーワードを1ページで対策すると決めたら、次は「どうやって記事にSEOキーワードを自然に盛り込むか」を考えましょう。
ここで注意すべきは、両方のキーワードを不自然に「詰め込む」ことです。
詳しくはこちら:
SEOキーワードの入れ方を徹底解説!検索順位が上がるコツを紹介
タイトル・見出しへ自然に含める
最も重要なキーワード(通常、検索ボリュームが最も大きいもの)をメインとし、もう一方は自然な形で盛り込みましょう。
- NG例(詰め込みすぎ):
- 「鉛筆 削り方 と とがらせ方!鉛筆を削るとがらせ方のコツ」
- → 不自然で読みにくい。
- OK例(メイン+サブ):
- 「鉛筆の削り方のコツ5選!鋭くとがらせる方法も解説」
- → メインの「削り方」を軸にしつつ、サブの「とがらせる」を自然な日本語として組み込んでいる。
見出し(H2, H3)も同様です。すべての見出しにキーワードを入れる必要は全くありません。
読者が求める答え(例:「カッターでの削り方」「芯の硬さ別のコツ」など)を見出しにする方が重要です。
同義語を最大限に活用する
Googleは文脈を理解しているため、同じ単語を繰り返す必要はありません。
例えば「鉛筆 削り方」と「鉛筆 とがらせ方」の両方で対策したい場合、本文中では以下のように自然な言葉に置き換えて説明を充実させます。
- 「削り方」「とがらせ方」
- 「研ぎ方」「鋭くする」「芯を出す」
- 「シャープナー」「鉛筆削り」
このように同義語や言い換え表現を豊かに使うことで、文章が自然になるだけでなく、ユーザーが使う様々な言葉遣いの検索クエリ(検索意図)を幅広くカバーできます。

ラッコキーワードの類語・同義語機能を使えば、同義語をかんたんに取得できます!
共起語を取り入れる
「鉛筆の削り方」というテーマについて書くならば、当然「カッター」「ナイフ」「デッサン」といった関連する言葉(共起語)が登場するはずです。
これらの共起語を記事に自然に盛り込むと、Googleから「この記事は【鉛筆の削り方】について詳しいページだ」と評価され、「鉛筆 削り方」はもちろん、「鉛筆 とがらせ方」や「鉛筆 研ぎ方」といった複数のキーワードでの上位表示に繋がります。

ラッコキーワードでは無料で共起語を取得できます。
上位にランクインしているページがどんなキーワードを使っているかチェックしてみましょう!

キーワードの詰め込みすぎに注意!

最後に絶対に行ってはならない行為について紹介します。
キーワードスタッフィング(過剰な詰め込み)は厳禁です。
キーワードスタッフィングとは、検索順位を操作する目的で、キーワードを不自然に詰め込むスパム行為です。
- NG例:
- 「鉛筆の削り方です。この鉛筆の削り方は、とがらせ方としても有効です。鉛筆 削り方 とがらせ方 ならこの記事。」(不自然な繰り返し)
- 背景色と同じ色でキーワードを羅列する(隠しテキスト)
これらの行為はGoogleのガイドライン違反であり、順位を大幅に下げる原因となります。
重要なのはキーワードの「数」ではありません。
常に「この記事は、読者の悩みを本当に解決しているか?」という「読者ファースト」の視点を忘れないでください。
参考:SEOキーワードは多すぎると逆効果?適切な数や上位表示を狙う方法も解説!
まとめ:複数キーワード対策で上位表示を狙うには

この記事では、「複数のSEOキーワードを1ページで対策するか?」を判断する基準・やり方と、具体的なSEOキーワードの入れ方・注意点を解説しました。
- 「1ページ1キーワード」ではなく、「1ページ1テーマ」
- 対策したい複数のキーワードが「1テーマ」か「別テーマ」かを見極める。
- 別テーマか1テーマかの判断基準は、
- 検索意図は同じか?(最重要)
- 競合上位サイトは同時に扱っているか?(同時ランクインキーワードでチェック!)
- 1テーマ・複数キーワードで1つの記事を書くときは、
- メインキーワードを軸にタイトル・見出しを設計する。
- 他のキーワードは「同義語」や「言い換え表現」として自然に盛り込む。
- 詰め込み(キーワードスタッフィング)は絶対にしない。

Google検索で上位表示を獲得するためには、「想定SEOキーワードで検索→記事に着地した読者の悩みを解決できるコンテンツ」を作成するのが大事です。
ユーザーのためになる記事を作成して、たくさんの上位表示・アクセスを獲得しましょう!