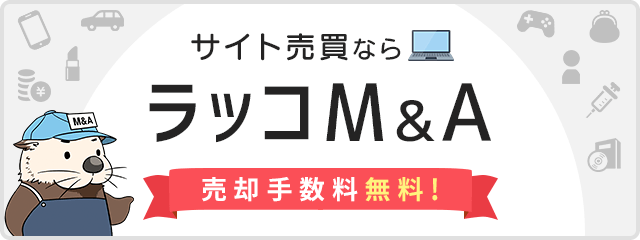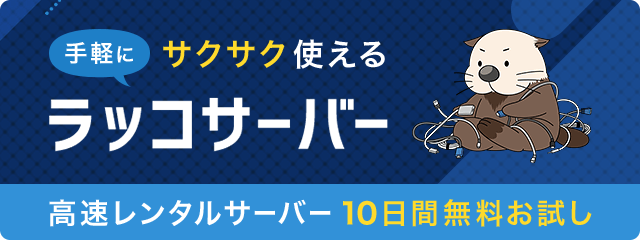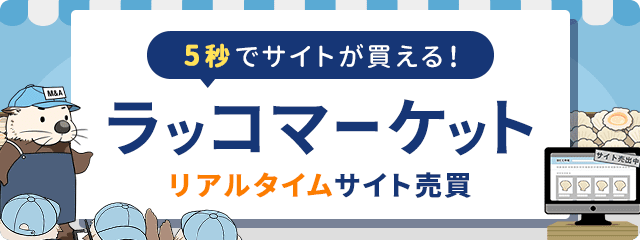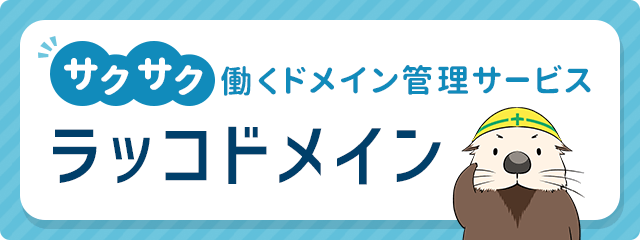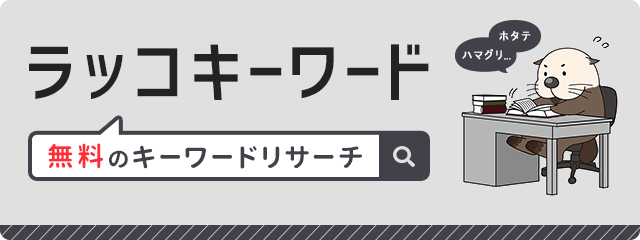SEO対策で記事を作成する際、「SEOキーワードは多く書けば書くほど良いのでは?」と疑問に思ったことはありませんか?
結論から言うと、SEOキーワードは多すぎると逆効果です。
かつてのSEOではキーワードを詰め込む手法が有効だった時代もありますが、現在は「ユーザーにとって価値があるか」が重要となっています。
また、キーワードを不自然に詰め込みすぎると読みにくくなるだけでなく、Googleから「品質の低いコンテンツ」と判断され、検索順位が下がるペナルティを受けるリスクすらあります。
本記事では、SEOキーワードが多すぎると良くない理由や適切なキーワード数、上位表示を狙うための具体的な方法について解説します。

この記事を読めば、適切なSEOキーワードの使い方がわかり、上位表示も狙えるような「価値のあるコンテンツ」を作成できるようになります!
【この記事を書いた人】
ラッコ株式会社・メディア運営担当者
SEOメディア運営を担当。
SEO初心者やWebライター向けに、わかりやすい解説記事を日々発信しています。
SEOキーワードが多すぎると逆効果?基本の考え方を解説

ここからは、SEOキーワードが多すぎると良くない理由について解説します。
SEOキーワードが多すぎる(キーワードスタッフィング)のはNG?
基本的な考えとして、SEOキーワードを多く詰め込みすぎるのはNGです。
ページ中にSEOキーワードを意図的かつ不自然なほど大量に盛り込む行為は「キーワードスタッフィング」と呼ばれています。
例えば、以下のようにSEOキーワードが頻繁に登場すると、ユーザーにとって読みにくい文章となってしまいます。
(例)
「SEOキーワード 多すぎ」でお悩みですか?この記事では「SEOキーワード 多すぎ」の対処法を解説します。「SEOキーワード 多すぎ」問題を解決し、SEO対策を成功させましょう。
また次項で詳しく説明しますが、SEOキーワードが多すぎるとGoogleからマイナス評価を受ける可能性もあり、注意が必要です。
Googleからの評価が下がるリスクとペナルティ
SEOキーワードが記事中に多く詰め込まれすぎていると、Googleに「スパムに関するポリシー」に違反していると判断される可能性があります。
その結果、以下のようなリスクが発生します。
- 検索順位の大幅な下落
- インデックスの削除(検索結果に表示されなくなる)
また、記事がペナルティを受けなかったとしても、読みにくい文章はユーザーの直帰率(ページを見てすぐに離脱する割合)を高める恐れがあります。
Googleはユーザーの行動も見ており、直帰率の高い記事は「ユーザーのニーズを満たしていない」と判断され、結果的に順位が下がる要因となるのです。
SEOキーワードは「1ページ1キーワード」が鉄則
SEOの基本的な考え方として「1ページ = 1キーワード(1つの記事に1つの検索意図)」というルールがあります。
例えば「ラッコキーワード 使い方」というキーワードで上位表示を狙う場合は、記事の焦点を「ラッコキーワードの具体的な使い方と活用手順」に絞るべきです。
逆に1つの記事に複数の検索意図を詰め込んでしまうと、以下のような問題が発生してしまいます。
- ユーザー側:「この記事は結局何が一番言いたいのか」が分からない。
- Google側:「この記事が何のテーマで最も権威性があるのか」を判断しにくい。

関連するキーワード(例:「ラッコキーワード 使い方」で上位表示を狙おうとしている記事に、「ラッコキーワード 無料」「ラッコキーワード 代替ツール」の解説を付け足す)を記事に含めるのは有効ですが、あくまでメインテーマの内容を補足・強化する程度に留めましょう。
SEOキーワードの数より重視すべき要点とは?

記事を作成する上で重要なのは、SEOキーワードの数ではなく「コンテンツの質」です。
ここからは具体的に重視すべき点をご紹介します。
ユーザーの「検索意図(ニーズ)」を満たすコンテンツになっているか
最も重要なのは、ユーザーがそのキーワードで検索した「目的」や「知りたいこと」を深く理解し、その答えを的確に提供することです。
例えば「ラッコキーワード 使い方」と検索するユーザーは、次のような疑問や悩みを持っていると考えられます。
- ラッコキーワードって、どうやって使うの?
- 登録やログインは必要?無料で使える?
- 検索ボリュームや関連キーワードはどこで確認できる?
- 他のキーワードリサーチツールとどう違うの?
- 効果的な使い方のコツや注意点は?
そのSEOキーワードでGoogle検索するユーザーが持っている疑問(検索意図)に対して、できるだけ分かりやすく、過不足なく答えるコンテンツこそがGoogleに評価されるコンテンツなのです。
コンテンツの「網羅性」と「専門性」を高める
検索意図を満たすためには、網羅性と専門性が重要です。
- 網羅性: ユーザーがメインの疑問を解決した後、次に抱くであろう関連する疑問にも先回りして答える。
- 専門性: 表面的な情報だけでなく、なぜそうなるのかという理由や、具体的な対処法、信頼できる情報源(E-E-A-T: 経験・専門性・権威性・信頼性)に基づいた解説を加える。
記事の網羅性を高める方法の1つとして、「関連キーワード」から把握した、ユーザーが知りたいであろう情報を盛り込むことが挙げられます。
関連キーワードとは、特定の検索キーワードと意味や文脈・ユーザーの検索行動などの面で深い関係を持つキーワード群のことです。詳細については以下の記事をご確認ください。
関連キーワードとは?SEO効果を最大化する仕組み・調べ方・活用ツールを解説
弊社が提供しているラッコキーワードの「関連キーワード」機能では、この関連キーワードを一括で大量に取得することができます。

また、各キーワードに対するSEO難易度や月間検索数も確認できるため、実際にどのキーワードを取り入れるかという点でも参考になります。

ラッコキーワードは日本語キーワードの出力量No.1を誇るため、コンテンツの網羅性を高めたい人にはピッタリです!
SEOキーワードは「自然な文章構成」を保ちながら含める
文章を作成する際はSEOキーワードを意識しがちですが、日本語として不自然な文章になってはいけません。
(良い例)
ラッコキーワードの使い方を理解すれば、記事のキーワード選定がぐっと効率的になります。
関連キーワードを調べることで、読者が実際に検索している言葉を把握できるでしょう。
その結果、検索意図に合った質の高い記事を作成できるようになります。
(悪い例)
ラッコキーワード 使い方を知るには、ラッコキーワード 使い方を調べることが大切です。
ラッコキーワード 使い方を理解すれば、ラッコキーワード 使い方が上達します。
そのため、ラッコキーワード 使い方を意識して記事を書くと良いでしょう。
文章は常に「ユーザーファースト」を心がけ、声に出して読んでも違和感のない、自然で読みやすいコンテンツを作成することが大切です。

可読性の高いコンテンツはユーザーの満足度を向上させ、直帰率の低下にも繋がるため、Googleから良い評価を受けやすくなります。
SEOキーワードを効果的に配置する場所と入れ方のコツ

SEOキーワードは配置する場所も重要です。ユーザーやGoogleが「この記事は何について書かれているのか」をすぐ理解できるよう、効果的な場所に配置しましょう。
タイトル冒頭にメインキーワードを設定
タイトル(titleタグ)は、SEOにおいて最も重要な要素の1つです。特にユーザーは検索結果画面でタイトルの冒頭を見て、自分に必要な情報があるかを判断しています。
タイトルにSEOキーワードを配置する際は、以下を意識するようにしましょう。
- メインキーワードは、できるだけタイトルの前半(冒頭)に含める。
- クリックしたくなるような、記事の内容を的確に表すタイトルにする。
SEOキーワードを含んだ記事タイトルを効率よく作成したい場合は、ラッコキーワードの「AI記事タイトル生成」機能もオススメです。

記事タイトル案を一気に20個提案してくれるため、効率的にタイトルの作成を行うことができます。

気に入ったタイトルがあれば、そのまま「見出し生成」ボタンで見出しもサクッと作成することができます!
見出し(H2・H3)に自然な形で関連キーワードを含める
見出し(h2・h3タグなど)は記事の骨組みであり、いわゆる「目次」のような役割を果たしています。
SEOキーワードを見出しに適切に入れることで、ユーザーは読みたい箇所へすぐに移動でき、Googleも記事全体の構成を理解しやすくなるといったメリットがあります。
実際に見出しにSEOキーワードを配置する際は、以下を意識するようにしましょう。
- メインキーワードや関連キーワードを、見出しの意図を損なわない範囲で自然に含める。
- 見出しを見ただけで、その項目に何が書かれているか分かるようにする。
また、SEOキーワードを含んだ見出しを作成したい場合は、ラッコキーワードの「AI記事見出し生成」機能もオススメです。

上記のように、SEOキーワードと記事タイトルに沿った見出し案を短時間で提示してくれるため、非常に便利です。

「AI記事タイトル生成」や「AI記事見出し生成」は無料(※1日の回数制限あり)で使用できるため、まずはお試しで使ってみるのもオススメです!
注意点として、ツールで生成したタイトル・見出しはそのまま使用するのではなく、自然な表現・言い回しとなるように手動修正するようにしましょう。
メタディスクリプションはクリック率(CTR)を意識
メタディスクリプションは、検索結果のタイトル下に表示される記事の要約文です。検索順位への直接的な影響は低いとされていますが、検索結果のクリック率(CTR)に大きく影響します。

メタディスクリプションを作成する際は、以下の点を考慮することが大切です。
- 記事の内容を簡潔に(120文字程度)まとめる。
- メインキーワードを含めつつ、ユーザーが「この記事を読みたい」と思うような魅力的な文章にする。
(作成例)
SEOキーワードは多すぎると逆効果です。不自然な詰め込みはGoogleからペナルティを受け、順位下落のリスクも。この記事では、多すぎるのがNGな理由、適切なキーワード数の考え方(1ページ1キーワード)や、上位表示を狙うための質を高める方法を解説します。

メタディスクリプションを作成する際はChatGPTやGeminiといったAIツールを使用するのが効率的です。
以下の記事で具体的な手順を解説しているほか、SEOキーワードを効果的に配置する方法についても紹介しているので参考にしてください!
【おすすめ記事】
SEOキーワードの入れ方を徹底解説!検索順位が上がるコツを紹介
SEOキーワード数のチェック方法

ここからは、SEOキーワード数をチェックする方法についてご紹介します。
現代のSEOにおいてキーワード数の重要性は低くなっています。むしろ、コンテンツの質や網羅性・読みやすさといった部分を意識することが大切です。
キーワード出現率とは
キーワードがページ全体にどれくらい含まれているかを示す言葉として「キーワード出現率」があります。
このキーワード出現率とは、ページ全体の総単語数に対し、特定のキーワード(SEOキーワードなど)が何%含まれているかを示す割合のことです。
一般的には、キーワード出現率が2~3%の場合「適切である」といわれています。実際の算出方法は以下の通りです。
【計算方法】
キーワード出現率(%)= 特定のキーワードの出現回数 ÷ ページ全体の総単語数 × 100
(例)
・ページ全体の単語数が1,000語
・SEOキーワード「SEO対策」の出現回数が20回
上記の場合、キーワード出現率は (20 ÷ 1000) × 100 = 2% となります。

キーワード出現率は、あくまでも「不自然なほどキーワードを詰め込みすぎていないか」という点を確認する程度に留めましょう。
SEOキーワード数のチェック方法(無料ツール)
特定のキーワードがページ全体にどのくらい含まれているか(=キーワード出現率)は、ツールを使うことで簡単にチェックできます。
以下では、無料で使用できるキーワード数チェックツールを4つご紹介します。
ohotuku

ohotukuは、URLまたはキーワードを入力するだけで、その中に含まれる単語の出現回数と出現率(%)を表示してくれるツールです。
キーワード数が調査できるツールとしては有名で、特に手軽にキーワードの数を調べたいという時に最適です。
- 特徴:
- 操作が簡単で、手軽にすぐ調査できる。
- キーワードの出現率がグラフで表示されるため、視覚的にわかりやすい。
- 余計な機能がなく、キーワードの出現頻度だけを素早く知りたい場合に便利。

とにかく気軽にキーワード数を確認したいという人にはオススメです!
ファンキーレイティング (FunkeyRating)

ファンキーレイティングは、URL・テキストからコンテンツ全体で特定のキーワードがどのくらいの割合で含まれているかを分析できるツールです。
キーワード数を確認する際、目標とする出現率(%)に対し、あと何個キーワードを増減すればよいか(調整数)を自動で算出できます。
- 特徴:
- 狙いたいキーワードと目標の出現率を設定することで、その目標を達成するために必要なキーワードの「調整数」が表示される。
- URL・テキスト入力(記事文章)の両方に対応。

URLだけでなく長文テキストでも調査できるため、「記事を公開する前にキーワード数をチェックしたい」という時に役立ちます!
SEOチェキ!

SEOチェキ!はURLを入力するだけで、そのサイト(ページ)の基本的なSEO状況を多角的かつ一覧で表示してくれるツールです。
キーワード数が確認できるのはもちろん、サイトに関する基本情報も可視化できるため、SEOの初期調査としても使えます。
- 特徴:
- URLを入力するだけですぐに結果が分かる。
- キーワード数以外にも、以下の多様な情報が取得できる。
- 内部要因:タイトル、メタ情報など
- 基本情報:最終更新日時、ファイルサイズ、読み込み時間
- インデックス状況:Google・Yahoo! JAPAN等のインデックス数
- リンク状況:発リンク数(内部/外部)
- ドメイン情報:利用ホスト、ドメイン登録日
- ソーシャル:Facebookの「いいね!」数など

キーワード数だけでなく、同時にほかの基本的なSEO情報も確認したいという方にオススメです!
キーワード出現率分析ツール(LYNX)

キーワード出現率分析ツール(LYNX)は、URLからサイト内に出現するキーワードの数を分析できるツールです。
他のツールと異なり、該当のキーワードがタイトル・メタディスクリプションに含まれているかといった点も確認できます。
- 特徴:
- キーワード数以外に、該当のキーワードがタイトルやメタディスクリプションに含まれているかも確認できる。
- リッチな見た目で使いやすい。

SEOキーワードをタイトルやメタディスクリプションに入れることは、検索エンジンにページの関連性を正しく伝えるほか、クリック率(CTR)の向上にも繋がるため重要です!
まとめ

今回は、SEOキーワードが多すぎると逆効果なのかについてご紹介しました。
結論として、基本的にSEOキーワードが多すぎるのはNGです。不自然なキーワードの詰め込み(キーワードスタッフィング)はGoogleからの評価を下げ、読者離れを引き起こす可能性もあります。
重要なのは、SEOキーワードの数ではなく「コンテンツの質」です。
- 検索意図の充足:ユーザーの検索目的を理解し、適切な回答を提供。
- 網羅性と専門性:関連する疑問や、信頼できる情報を取り入れる。
- 自然な文章構成:SEOキーワードを詰め込まず、ユーザーファーストな文章を意識。
- 効果的なキーワード配置:記事内容が伝わりやすいよう、効果的な場所に配置。
記事を作成する際は、常に「読者にとって本当に価値のある情報は何か?」を第一に考えることを意識しましょう。

コンテンツの質を高めるなら「ラッコキーワード」がおすすめです!
関連キーワードや共起語の検索といったキーワードリサーチ機能が充実しており、読者のニーズを深く掘り下げられます。
また、タイトル・見出し生成AI機能も備わっており、効率的・効果的に記事を作成できます!